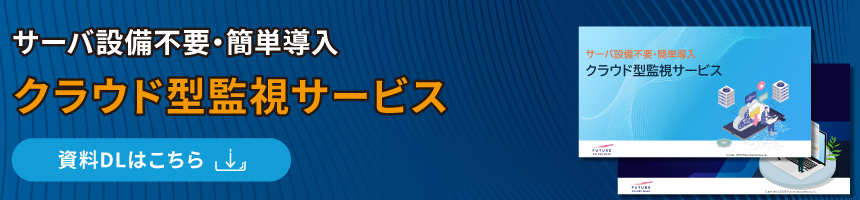IT資産管理|実は緊密なシステム監視とIT資産管理の関係性
はじめに:IT資産管理とシステム監視、別々に管理していませんか?
企業のIT担当者の皆様は、日々多くの業務に追われていることでしょう。PCやサーバーの棚卸し、ソフトウェアライセンスの更新、そして、システムが正常に稼働しているかを監視するアラート対応…。これらを「IT資産管理」と「システム監視」という、それぞれ独立した業務として捉えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、デジタルトランスフォーメーション(DX)が叫ばれ、クラウド利用やリモートワークが当たり前になった現代において、IT環境はますます複雑化しています。このような状況で、IT資産管理とシステム監視が分断された「サイロ化」状態にあると、業務の非効率化を招くだけでなく、深刻なセキュリティリスクや無駄なコストを生む温床になりかねません。
実は、IT資産管理とシステム監視は、企業ITの健全性を保つための「車の両輪」とも言える、非常に緊密な関係にあります。
前回『IT資産管理|情シス担当者が知っておくべき基本の「キ」』では、IT資産基本を解説いたし増したが、本記事では、なぜ今この二つの連携が重要なのか、そして連携によってどのようなメリットが生まれ、具体的にどう始めればよいのかを、分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、日々の管理業務の先に広がる「戦略的なIT管理」への道筋が見えているはずです。
第1章:そもそもIT資産管理とシステム監視とは?
まず、両者の基本的な役割と目的を再確認しておきましょう。それぞれの守備範囲を正しく理解することが、連携の重要性を知る第一歩となります。
IT資産管理の目的:コスト削減、コンプライアンス、セキュリティ強化
IT資産管理とは、組織が所有するIT資産を正確に把握し、そのライフサイクル(購入から廃棄まで)全体を最適化するための活動です。管理対象は多岐にわたります。
ハードウェア:PC、サーバー、ネットワーク機器(ルーター、スイッチ)、プリンターなど
ソフトウェア:OS、オフィススイート、業務アプリケーション、各種ツールのライセンス
その他:クラウドサービスのアカウント、ドメイン、各種契約情報など
これらの情報を「IT資産管理台帳」として一元管理することが基本です。その目的は、単に「モノの数を数える」ことではありません。
- コスト最適化
- 不要なハードウェアの購入抑制や使われていないソフトウェアライセンスの解約
- これらによりITコストを最適化することが可能です。
- コンプライアンス遵守
- ライセンス違反による訴訟リスクや、各種法令・ガイドラインへの準拠を確実にします。
- セキュリティ強化
- 利用しているソフトウェアやOSのバージョンの把握することで脆弱性情報を把握できます。
- これにより情報漏洩などのセキュリティインシデントを未然に防ぎます。
IT資産管理は、いわばITインフラの「静的な状態」を正確に記録・管理する活動と言えるでしょう。
システム監視の目的:安定稼働、障害の予兆検知、パフォーマンス維持
一方、システム監視は、サーバーやネットワーク、アプリケーションが正常に稼働し続けているかをリアルタイムでチェックする活動です。
主な監視対象
- サーバ(物理サーバ/仮想サーバ)
- ネットワーク機器(UTM/ルータ/スイッチハブ)
- ストレージシステム
- クラウドサービス/Webサービス
- その他
主な監視項目
- CPU使用率
- メモリ使用率
- ディスク使用率
- ネットワークトラフィック
- Webサイトの応答速度
- サービスのプロセス死活
- エラーログの監視
- その他
これらの情報を常に監視し、異常が発生したり、事前に設定した閾値を超えたりした場合に、管理者にアラートを通知するのが主な役割です。
- 安定稼働の維持
- 障害をいち早く検知し、サービス停止などの機会損失を最小限に抑えます。
- 障害の予兆検知
- 「ディスク容量が90%に達した」「メモリ使用量が急増している」
- といった本格的な障害に至る前の兆候を捉え、プロアクティブ(事前)な対応を可能にします。
- パフォーマンス維持
- システムの性能劣化を把握し、ユーザー体験の低下を防ぎ、リソース増強などの計画立案に役立てます。
システム監視は、ITインフラの「動的な状態」を常に追いかけ、その健全性を保つための活動と言えます。
このように、管理対象や目的が異なるため、両者は別物として扱われがちです。しかし、次の章では、この「静的情報」と「動的情報」が交わる点にこそ、大きな価値が眠っていることを解説します。
第2章:IT資産管理とシステム監視の"意外な"接点
IT資産管理とシステム監視が連携すると、具体的にどのような化学反応が起きるのでしょうか。日常業務で起こりがちな3つのシナリオを通して、その接点を探っていきましょう。
接点1:ハードウェア情報 - 「サーバーが重い!」その原因と対策が瞬時にわかる
【シナリオ】システム監視ツールから「WebサーバーAのCPU使用率が5日間連続で95%を超過」というアラートが上がってきました。
- 連携がない場合
- 担当者はまず、サーバの情報を集めるため保管されているそれぞれの資料を探します。
- サーバーAのスペックを確認するために過去の資料
- いつ購入した機器なのかを調べるために購入履歴を調査
- 該当機器の保守契約がどうなっているかを確認
- などなど。
- 別々のファイルやシステムで管理されている情報を調べて回る必要があります。
- これでは原因究明と対策判断に必要な情報収集に多くの時間と手間がかかります。
- 連携がある場合
- 監視システムのアラート画面に表示されたホスト名「WebサーバーA」から、IT資産管理台帳の情報が自動的に紐づけられます。担当者はワンクリックで以下の情報を即座に把握できます。
- 例)
- スペック: CPU、メモリ、ディスク容量
- 購入日: 2019年10月(導入から6年経過)
- 保守契約: 今月末で満了
- 担当部署: 営業企画部
- 物理的な設置場所: 第2サーバルーム、A-3ラック
この情報により、「単なるアクセス集中ではなく、機器の老朽化による性能限界である可能性が高い。保守契約も切れるため、早急にリプレース計画を立てるべきだ」という的確な判断を、わずか数分で下すことができます。
接点2:ソフトウェア情報 - 「そのライセンス、本当に必要?」無駄なコストを炙り出す
【シナリオ】 経理部門から、来期のIT予算策定のために高価な分析ソフトウェアのライセンス更新について相談がありました。現在50ライセンスを契約しており、年間コストは数百万円に上ります。
- 連携がない場合
- 担当者は利用者全員に「このソフトウェア、使っていますか?」とヒアリングして回ります。
- しかし、正確な利用実態は把握しづらく、「念のため必要」という回答も多いため、結局は現状維持となり、無駄なコストが垂れ流されがちです。
- 連携がある場合
- システム監視(またはクライアントPCの操作ログ監視)ツールで、対象ソフトウェアの「起動状況」をモニタリングします。
- その稼働実績データと、IT資産管理台帳の「ライセンス割り当て情報」を突き合わせます。
- その結果、「ライセンスが割り当てられている50名のうち、過去3ヶ月間で一度も起動していないユーザーが15名いる」という客観的な事実が判明しました。
- このデータを基に、本当に必要なライセンス数を35に削減する提案ができ、大幅なコスト削減を実現できます。
接点3:セキュリティ - 「誰のPC?」正体不明のデバイスを即座に特定・遮断
【シナリオ】 ネットワーク監視ツールが「資産管理台帳に登録されていない、不審なMACアドレスを持つデバイスが社内ネットワークに接続された」ことを検知しました。
- 連携がない場合
- 情報システム部は、どのスイッチのどのポートに接続されているかを調査し、フロアを歩き回って物理的な機器を探し出す必要があります。
- 調査している間に、そのデバイスがマルウェアを拡散させてしまうかもしれません。
- 連携がある場合
- 検知した情報をトリガーに、IT資産管理台帳とリアルタイムで照合が行われます。
- 台帳に存在しないデバイスであることが確定すると、即座にネットワーク機器と連携し、該当するポートを自動的にシャットダウン(遮断)します。
これにより、私物PCの無断接続や、悪意のある第三者による不正アクセスといった「シャドーIT」のリスクを未然に防ぎ、インシデントへの対応を自動化・迅速化できます。
第3章:連携で実現する3つの大きなメリット

前章で見たように、IT資産管理とシステム監視の連携は、日々の課題を解決するだけでなく、企業全体に大きなメリットをもたらします。ここでは、そのメリットを「セキュリティ」「コスト」「運用効率」の3つの観点から整理します。
メリット1:セキュリティレベルの向上
連携によって、よりプロアクティブで多層的なセキュリティ対策が可能になります。
- 脆弱性のあるIT資産の迅速な特定と対策
- IT資産管理台帳には「OSのバージョン」や「特定ソフトウェアのバージョン」が記録されています。
- ここに新たな脆弱性情報が公開された際、該当する資産を即座にリストアップできます。
- さらにシステム監視データと組み合わせることで、「外部との通信が活発なサーバー」など、リスクの高い資産から優先的にパッチを適用するといった、効果的な対策が打てます。
- シャドーITの撲滅
- 前述の通り、許可なく接続されたPCやIoT機器などを即座に検知し、ネットワークから遮断できます。
- これにより、管理外のデバイスが原因で発生する情報漏洩やウイルス感染のリスクを大幅に低減します。
メリット2:ITコストの最適化
勘や経験に頼ったIT投資から、データに基づいた賢いIT投資へとシフトできます。
- ハードウェアの計画的な更新によるTCO削減
- 機器の性能情報(動的)と資産情報(静的)を組み合わせることで、ハードウェアのライフサイクル全体を見通した管理が可能になります。性能が限界に近く、保守コストも高くなっている老朽化した機器を適切なタイミングでリプレースすることで、突発的な故障によるビジネス損失を防ぎ、TCO(総所有コスト)を最適化します。
- ソフトウェアライセンス費用の適正化
- ソフトウェアの実際の利用状況を正確に把握することで、余剰ライセンスを削減できます。
- 逆に、ライセンス数が不足している「ライセンス違反」状態を早期に発見し、コンプライアンスリスクを回避することも可能です。
メリット3:運用業務の劇的な効率化
IT担当者の日々の業務負担を大幅に軽減し、より戦略的な業務に集中する時間を生み出します。
- 障害対応の迅速化(MTTRの短縮)
- 障害アラートが発生した際に、その原因究明に必要な情報(機器のスペック、構成情報、設置場所、担当者など)がすべて紐づいているため、初動対応が格段に速くなります。
- これにより、MTTR(平均修復時間)が短縮され、ビジネスへの影響を最小限に食い止められます。
- 棚卸し作業の自動化と精度向上
- 年に一度の一大イベントであったPCやサーバーの棚卸し作業も、様変わりします。ネットワークに接続されている機器のインベントリ情報(ハードウェア構成、インストールソフトなど)を自動収集し、IT資産管理台帳と定期的に突合。
- これにより、手作業による確認作業が不要になり、常に最新かつ正確な資産情報を維持できます。
第4章:明日から始める連携の第一歩
「連携のメリットは分かったけれど、何から手をつければいいのか…」と感じる方も多いでしょう。大規模なツール導入だけが連携の方法ではありません。ここでは、スモールスタートで始められる3つのステップをご紹介します。
- まずは今使っているツールの連携機能を確認してみる
- 意外と見落としがちですが、現在利用中のIT資産管理ツールやシステム監視ツールに、外部ツールとの連携機能(API)や、データのエクスポート機能(CSV形式など)が備わっている場合があります。
- まずはツールのマニュアルや公式サイトを確認し、どのようなデータ連携が可能か調べてみましょう。
- 両方のデータをExcelなどに出力し、手動で突き合わせてみる
- もしツールに直接の連携機能がなくても、諦める必要はありません。
- それぞれのツールから資産情報と監視データをCSV形式でエクスポートし、Excelなどの表計算ソフトで手動で突き合わせてみましょう。「ホスト名」や「IPアドレス」をキーにしてVLOOKUP関数などを使えば、簡易的な連携が可能です。
- この作業だけでも、「アラートが頻発しているのは、決まって購入後5年以上経過した古いPCだ」といった、これまで見えなかった新たな発見があるはずです。
- 統合管理ツールの検討(どのような選定軸で見るべきか)
- 将来的に本格的な連携を目指すのであれば、統合管理ツールの導入も視野に入ってきます。その際は、以下のような選定軸で検討することをおすすめします。
- 拡張性: 自社の規模や管理対象の増減に柔軟に対応できるか。
- 網羅性: オンプレミスだけでなく、クラウド資産(IaaS/SaaS)も一元管理できるか。
- 操作性: ダッシュボードは見やすいか、直感的に操作できるか。
- サポート体制: 導入支援やトラブル発生時のサポートは充実しているか。
最初から完璧を目指す必要はありません。まずは自社の課題に合った、スモールスタートできる方法から試してみることが重要です。
まとめ:サイロ化を脱却し、戦略的なIT管理部門へ

これまで見てきたように、IT資産管理とシステム監視は、それぞれが独立した業務ではなく、互いの情報を補完し合うことで、その価値を何倍にも高めることができる密接な関係にあります。
IT資産管理が提供する「静的な台帳情報」
システム監視が提供する「動的な稼働情報」
この二つを掛け合わせることで、ITインフラ全体を正確に、そしてリアルタイムに可視化することが可能になります。それは、日々の運用業務を効率化するだけでなく、セキュリティを強化し、無駄なコストを削減し、データに基づいた的確なIT投資判断を支援する、まさに「戦略的なIT管理」の実現に他なりません。
もし今、あなたの会社の管理体制が分断されているのであれば、それは大きなチャンスかもしれません。 まずは、あなたの手元にあるIT資産管理台帳と、監視ツールのアラート画面を並べて眺めてみてください。きっとそこには、会社のITをより良くするためのヒントが隠されているはずです。
関連サービス
運用コンサルティングサービス
IT戦略・システム企画サポート
システムマネジメントサービス
監視・モニタリングサービス
システム運用代行サービス
社内情報システム運用・保守サポート