
SIEMによる不正アクセス対策とその効果~攻撃の兆候を“つなげて”見抜く仕組みとは~
前回の記事では、不正アクセスの概要とそのリスクについて解説しました。
今回はその対策の中でも、近年注目が高まっている SIEM(Security Information and Event Management) に焦点を当てて解説します。
また、併せて前回の『能動的サイバー防御とSIEMの親和性 ~ログ解析の決定的役割~』、不正アクセスの基本・基礎について解説した『「不正アクセス」とは? ―― 種類と脅威・対策を解説』も参考ください。
SIEMは、サーバー・ネットワーク・クラウド・端末などあらゆるシステムからログを収集・管理し、相関分析
することで、攻撃の兆候を早期に検出・対応できる仕組みです。
本記事では、SIEMの基本機能から導入のメリット、相関ルールの実例、運用上の注意点までを
体系的に紹介します。
「なぜ今、SIEMが必要なのか」「どのように活用すべきか」を実際の運用例を交えながら詳しく解説します。
不正アクセスとそのリスクを振り返る
まず、不正アクセスについて簡単におさらいしていきます。
不正アクセスとは、権限を持たない者が組織の情報システムに侵入し、
情報を窃取・改ざん・破壊する行為を指します。
その被害は技術的損失にとどまらず、信頼の失墜や財務的損害、法的リスクにもつながります。
主な影響
- 信頼の失墜:顧客・取引先からの信用が失われ、企業ブランドに長期的なダメージを負う
- 金銭的損失:調査・復旧・補償・罰金・業務停止による損害など、巨額のコストが発生
- 法的リスク:個人情報保護法やサイバーセキュリティ関連規制への違反により、
行政指導や刑事責任を問われる可能性
しかし、実際に不正アクセスの対策を進めていくと、現場では次のような課題が見えてきます。
- 各システム・製品がバラバラにログを出力し、全体像を統一的に把握できない
- EDR・IDS/IPS・FWなどの点在した検知を相関できず、「点」止まりの監視に陥る
- 事後調査において「どの経路から」「どの認証を突破して」「どの操作が行われたか」を追えない
このような断片化したログをつなぎ合わせて、攻撃の全体像を明らかにする仕組みこそがSIEMです。
SIEMとは?基本概念と機能
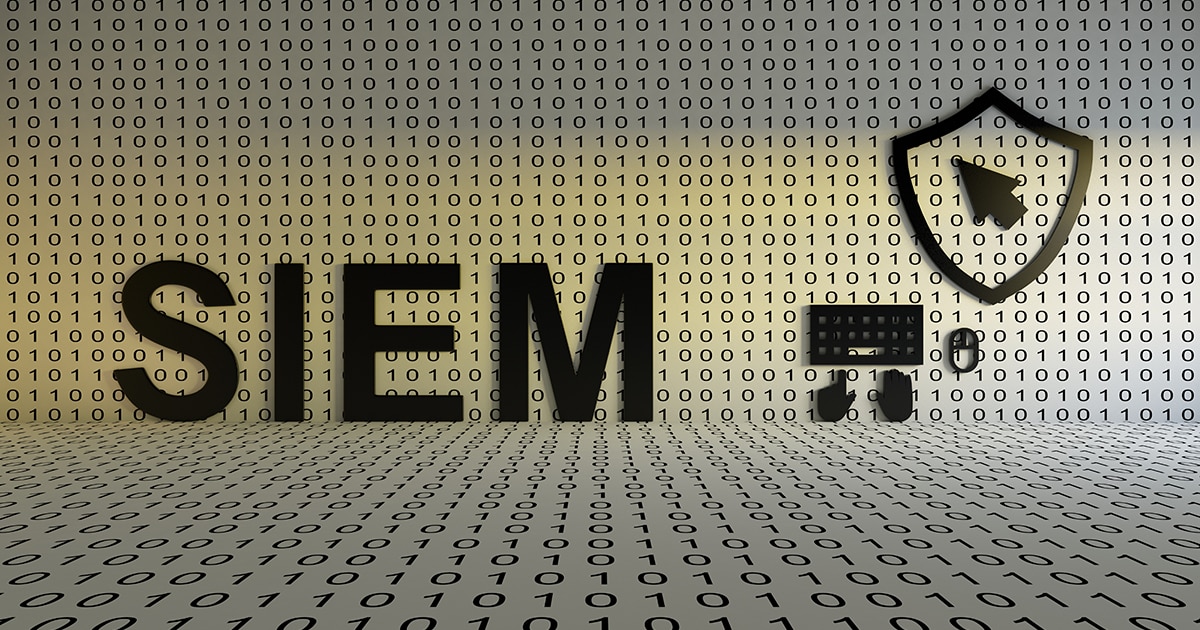
SIEM(Security Information and Event Management)とは、「セキュリティ情報管理(SIM)」と
「セキュリティイベント管理(SEM)」を統合した仕組みであり、組織全体のログを一元的に収集・管理し、
相関分析によって脅威の検知や分析を行うシステムです。
ネットワーク、サーバー、アプリケーション、クラウドサービスなど、あらゆるレイヤーから発生するログを集約し、リアルタイムに可視化・監視します。
これを活用することで、従来のように問題が起きてから対応する「事後調査型」ではなく、事前に兆候を捉える
「予兆検知型」の運用にシフトできます。
SIEMの基本的な機能については以下の通りです。
ログの集約・正規化・保存
SIEMの中核となるのが ログの収集・正規化・保存 機能です。
SIEMは、ファイアウォール、認証サーバ、EDR、クラウド監査ログなど、あらゆるソースからログを集約し、集めたログを共通フォーマットに変換(正規化)し、分析しやすい形で保存します。
さらに、WORMストレージやデジタル署名を組み合わせることで改ざん防止が可能となり、
「検索可能な証跡データ」として監査証跡に活用することもできます。
※WORM(Write Once, Read Many)とは、一度書き込んだデータを変更・削除できないように
するストレージ技術です。この技術では、データは保持期間が終了するまで改ざん不可の状態となるため、証跡や監査用データの保全に最適です。
そのため、SIEMなどのログ統合ツールでも採用されるケースが多くあります。
リアルタイム分析
SIEMの最大の強みは、複数のログを関連付けて分析し、異常を検知できる点です。
たとえば、連続するログオン失敗イベントのあとに、成功したログオンイベントを関連付けて、
「ブルートフォース攻撃が成功した可能性」を検知することができます。
また、最近は機械学習やUEBA(User and Entity Behavior Analytics)を活用し、
「通常時の行動(ベースライン)」から逸脱したパターンを自動的に検出することができる高機能なSIEMも
登場しています。
インシデント対応・自動化(SOAR連携)
検知した脅威はアラートとしてセキュリティチームに通知され、対応のトリガーとなります。
SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)と連携すれば、以下のような
自動対応も可能です。関連ログや端末情報の自動収集
マルウェア感染端末の自動隔離
チケット発行・通知の自動化
上記により、手作業中心であった対応を自動化し、検知から対応までの時間を大幅に短縮できます。
補足:UEBAとは
UEBAは、User and Entity Behavior Analytics(ユーザとエンティティの行動分析)の頭字語を取った
用語で、ユーザの行動をもとに高度な分析を行い、異常行動を検知するサイバーセキュリティツールの
分野です。それぞれの頭文字は、以下を意味します。
用語 | 説明 |
|---|---|
User(ユーザー) | UEBAは、ユーザのログインやアクセス、操作などの行動データを分析し、 |
Entity(エンティティ) | 「E(エンティティ)」という概念は2015年にガートナー社が導入しました。 |
Behavior(行動) | UEBAは、それぞれのユーザやデバイスが「通常どのように行動しているか」を |
Analytics(分析) | UEBAの中核はAIや機械学習による高度な分析です。大量のログを取り込み、 |
SIEMの導入メリットと役割
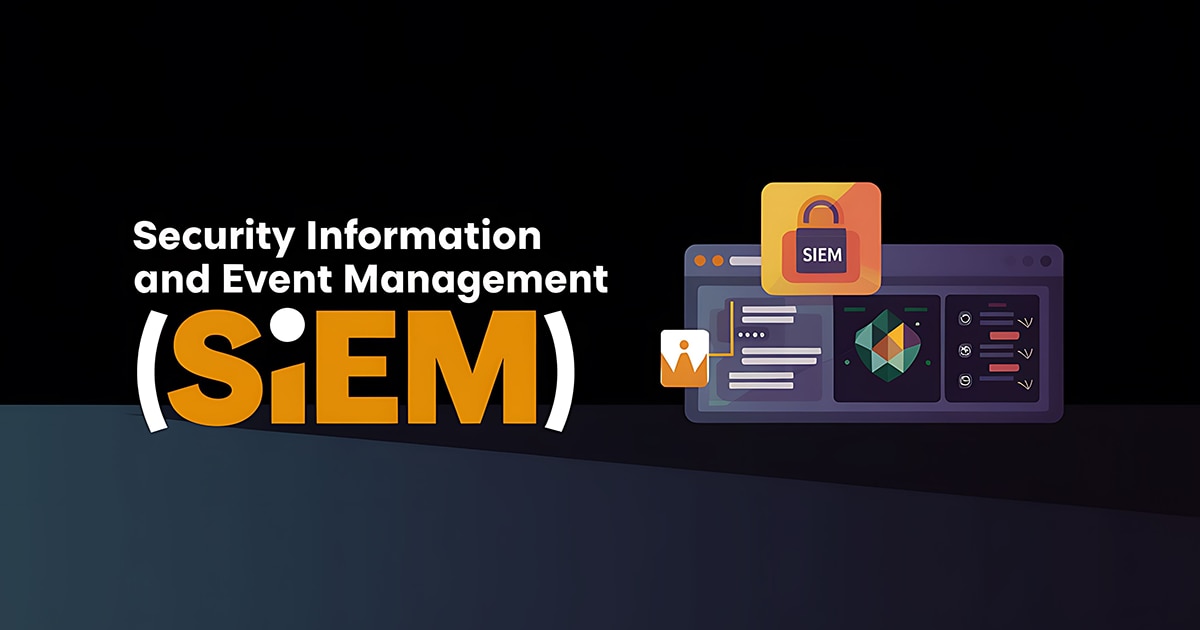
SIEMは単なる「ログ分析ツール」ではなく、組織全体のセキュリティイベントを一元管理し、検知・分析・対応を自動化するための統合基盤です。
ログの集約・正規化・相関分析・アラート生成・可視化といった一連のプロセスを統合することで、検知精度の向上や迅速な対応、運用の効率化をひとつの仕組みで実現します。
また、SIEMは、複数のセキュリティ製品(EDR、FW、WAF、クラウド監査ログなど)からイベントを収集し、共通スキーマで正規化・時系列整合を行うことで「攻撃の全体像」を可視化します。これにより、単発のアラートを超えた「攻撃連鎖の把握」や「横展開検知(Lateral Movementの可視化)」が可能となります。
SIEM導入による主な効果
SIEMの導入効果は、SOC(Security Operation Center)運用やインシデントレスポンスの観点から、次の5つに大別されます。
分類 | 効果 | 内容 |
検知精度の向上 | 相関分析により、単発アラートでは見落としてしまう攻撃のつながりを検知 | 攻撃全体の“ストーリー”を可視化。EDR・FW・クラウド監査ログを横断的に分析し、真の侵害イベントを抽出できる |
リアルタイム対応 | 異常検知から自動対応までを | SIEMがSOARと連携し、初動対応(端末隔離・チケット発行・通知)を |
運用効率化 | アラート集約・チケット自動化によりSOC負荷を軽減 | 重複アラートの統合・誤検知の削減により、分析工数を大幅に削減。 |
コンプライアンス対応 | ログ保全・監査証跡・アラート履歴を体系的に保存 | ISMS、FISC、PCI DSSなどのログ保全要件に準拠。 |
情報の可視化 | ダッシュボードによる | リアルタイムレポートにより、セキュリティ投資の効果やインシデント傾向を定量的に把握可能 |
SIEMと能動的サイバー防御の連携
SIEMのログ集約・相関分析機能は単なる監視にとどまらず、能動的サイバー防御と連携することで、
攻撃の兆候に基づく自動防御を実現できます。
能動的サイバー防御とは、攻撃の兆候を検知した時点で即座に防御アクションを実行し、
被害の拡大を防ぐ戦略です。
能動的サイバー防御の詳細はこちら
- 攻撃端末やアカウントを自動隔離
- 異常通信やマルウェアの拡散をリアルタイムで遮断
- 特権昇格や不正操作を即座に抑止
この仕組みにより、従来の「検知→手動対応」の流れでは間に合わなかった高度な攻撃にも対応可能です。
SIEMとの相互補完
SIEMと能動的サイバー防御は、お互いの役割を相互に補完し、「検知 → 分析 → 自動防御」の
サイクルを実現します。
SIEM | 能動的防御 |
|---|---|
複数ログの相関分析で脅威を検知 | 脅威情報をもとにリアルタイムで防御アクション |
ダッシュボードで状況を可視化 | 不審アクセスやマルウェア通信を遮断・隔離 |
SOAR連携による自動化 | チケット発行・通知・初動対応を即時実行 |
相関分析による高度な検知
SIEMは複数イベントを関連付けて「攻撃のストーリー」を可視化できます。
従来は個別製品のアラートを手作業で突き合わせる必要がありましたが、SIEMでは自動相関により
複合的な攻撃シナリオを検出することが可能です。
実例:不正アクセス検知ルール
No | 検知シナリオ | 条件 | トリガーアクション |
1 | ブルートフォース攻撃の成功を検知 | 同一アカウントで10回以上ログオン失敗 → 直後に成功 | 「Brute Force成功の疑い」 |
2 | 不審なVPN接続を検知 | 同一ユーザーが1時間以内に複数国からログイン | 「Impossible Travel検知」 |
3 | 権限昇格後の設定変更を検知 | 特権イベント(4672)+10分以内に設定変更(4732) | 「特権昇格後の不正操作」 |
4 | 異常なデータ転送量を検知 | 特定端末の送信量が通常平均の5倍以上 | 「データ持ち出しの疑い」 |
これらのシナリオは、単一ログでは異常と見なされにくい挙動を時間軸・ユーザー・ネットワーク経路の観点で
結びつけ、「侵入 → 横展開 → 権限奪取 → 情報持ち出し」といった一連の攻撃パターンを再現的に捉えることを可能にします。
このように、SIEMは断片化されたログを統合し、攻撃の全体像を見える化する“司令塔”のような役割を
果たします。
その結果、不正アクセスの早期検知や迅速な封じ込めが可能になります。
SIEM導入・活用事例

1. 大手金融機関の活用事例
某大手金融機関では、日々膨大に発生するログデータを人手で確認することが難しく、異常検知の遅延が課題となっていました。
そこでSIEMを導入し、全社のサーバ・ネットワーク・アプリケーションログを一元的に収集・分析する仕組みを構築しました。
特に「深夜帯の不審アクセス」や「短時間での大量ログイン試行」などを自動検出するルールを設定することで、
顧客データを狙った不正アクセスの早期発見を実現。
この結果、セキュリティ監視体制の強化とともに、顧客からの信頼性向上にもつながりました。
2. 小規模企業の活用事例
近年では、クラウドベースのSIEMソリューション(例:Microsoft Sentinel、Elastic SIEM、Splunk Cloudなど)の普及により、
中小規模企業でも導入しやすい環境が整っています。
某中小企業では、クラウドSIEMを採用することで、サーバーやネットワーク機器のログをクラウド上で自動収集し、可視化ダッシュボードから稼働状況や不審挙動をリアルタイムに監視可能にしました。
オンプレミス機器の保守コスト削減や、監視工数の削減により、限られたリソースでも高いセキュリティ運用水準を維持できるようになりました。
このように、SIEMは大企業だけでなく、スモールスタートでの導入にも十分な価値を発揮します。
SIEM導入のステップと注意点
SIEMを導入する際の基本的なステップと注意点について解説します。
SIEMを導入・運用する際には、単にツールを導入するだけでなく、自社のセキュリティ体制・運用能力に即した設計が不可欠です。
以下では、導入までの一般的なステップと、運用上の注意点を解説します。
導入ステップ
ニーズの明確化
自社がどのようなリスクに直面しているか(例:外部からの侵入、内部不正、クラウド利用拡大など)を整理し、
「どのようなログを監視すべきか」「どの範囲を可視化したいか」を明確にします。
製品・アーキテクチャ選定
オンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型など、組織の構成や規模に応じたSIEMを選定します。
分析機能・拡張性・コスト・運用サポートを比較検討し、将来的なスケールも考慮することが重要です。
ログ収集・正規化設計
各システムのログをSIEMで正しく認識・分析できるよう、収集方式(Syslog、API、エージェント等)と正規化ルールを設計します。
この段階でログ品質(時刻整合、フォーマット統一、不要ログ除外)を整えることが、後の分析精度を左右します。
アラート設計と相関ルール構築
アラートの閾値を適切に設定し、過検知(False Positive)や誤検知(False Negative)を抑えるルールチューニングを行います。
定期的にルールを見直し、新たな攻撃手法(TTPs)に追随できる運用体制を整えましょう。
運用・継続改善
導入後は、SOCやCSIRTなどの運用部門が中心となり、検知精度・レスポンス速度を定期的に評価します。
攻撃パターンの変化や新しいシステム追加に合わせて、ダッシュボードやルールをアップデートすることが重要です。
導入・運用上の注意点
専門知識の必要性
SIEMは高機能な一方で、ログ形式・相関ルール設計などに専門的な知識が求められます。
初期は外部パートナーやベンダーに構築支援を受けて導入することを推奨します。
マネージドSIEM(MSSP)を利用するのも現実的な解決策です。
誤検知・過検知の対応
検知ルールの初期設定では、誤検知(False Positive)が多発することがあります。
定期的なルール調整とホワイトリスト化を行い、SOCチームの分析負荷を軽減しましょう。
運用コストとスケーラビリティ
ログ量が増えるほどSIEMのストレージ・分析コストも上昇します。
重要ログを優先的に取り込み、低優先度データはアーカイブ化するなど、コスト最適化の設計が必要です。
SIEMは専門的な知識が求められる製品のため、導入から運用まで一気通貫でサポートしてくれる
外部パートナーを頼るのも有効です。
まとめ
本記事では、不正アクセス対策におけるSIEMの重要性や導入メリット、実際の活用事例、そして導入ステップと注意点について体系的に解説しました。
不正アクセスは年々巧妙化・長期化しており、従来の防御だけでは侵入の兆候を見逃してしまうケースも少なくありません。
こうした中で、SIEMは単なるログ管理ツールではなく、「検知・分析・対応」を一元的に行うセキュリティ中枢基盤として、侵入の早期検知や被害拡大の防止に大きな効果を発揮します。
また、クラウド利用やリモートワークの普及により境界防御の限界が明確になる今、社内ネットワークや端末、ユーザ操作などの活動を可視化し、相関分析することで**“不正アクセスを見逃さない仕組み”を構築できる点**も、SIEMの大きな強みです。
不正アクセス対策を本質的に強化するには、単発のツール導入ではなく、SIEMを中心とした継続的な監視・分析体制の整備が欠かせません。
セキュリティ運用の成熟度を高める第一歩として、ぜひSIEM導入を検討し、自社の防御力を次のレベルへ引き上げていきましょう。



