
IT資産管理|情シス担当者が知っておくべき基本の「キ」
はじめに:なぜ今、IT資産管理が「経営課題」なのか?
企業のあらゆる活動がITによって支えられている現代、情報システム部門(情シス)が担う役割は、もはや単なる「縁の下の力持ち」ではありません。その中でも、すべてのIT戦略の土台となるのが「IT資産管理」です。
かつては社内PCの台数把握やソフトウェアの棚卸しといった地味な業務と見なされがちでしたが、今やその重要性は飛躍的に高まり、企業の競争力や信頼性を左右する「経営課題」として認識され始めています。
この変化の最大の要因は、働き方の多様化とIT環境の複雑化です。
テレワークの常態化により、PC、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーターといった物理デバイスが社外へ分散しました。管理者の目が行き届かない場所での利用は、紛失・盗難による直接的な情報漏洩リスクはもちろん、セキュリティ対策が不十分な個人所有デバイス(BYOD)の業務利用や、許可されていないアプリケーションのインストールといった「シャドーIT」を誘発し、深刻なセキュリティインシデントの温床となり得ます。
さらに、SaaS(Software as a Service)に代表されるクラウドサービスの利用拡大は、資産管理の対象を物理的な「モノ」から、目に見えない「権利」や「契約」へと広げました。誰が、どのサービスの、どのプランを契約し、アクティブに使っているのか。退職者のアカウントが放置され、無駄なコストを支払い続けていないか。これらの管理が不十分な場合、コストの垂れ流しに繋がり、企業の収益性を確実に蝕んでいきます。
IT資産管理の不備は、単なる非効率ではありません。ソフトウェアライセンス監査で規約違反が発覚すれば、数百万、数千万円単位の損害賠償や追徴金を請求されるコンプライアンスリスクに直面します。また、正確な資産状況を把握できなければ、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のための適切なIT投資判断も行えません。
このように、IT資産管理はもはや単なる備品管理ではなく、セキュリティ、コンプライアンス、コスト最適化、そして経営戦略の実現を支える、極めて重要な経営基盤なのです。本記事では、IT資産管理の本質的な重要性を再確認し、その基本から具体的な実践プロセス、そして成功に導くための要点までを、体系的かつ詳細に解説していきます。
IT資産管理の基礎知識
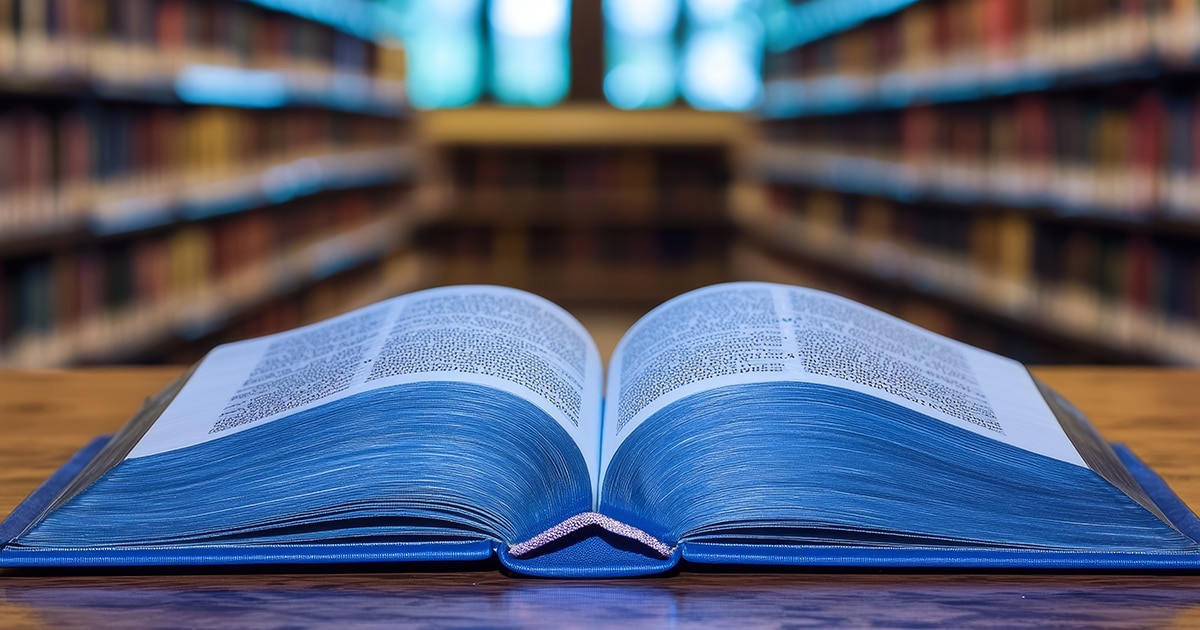
IT資産管理を効果的に実践するためには、まずその対象と目的、そしてグローバルな基準となっている考え方を正確に理解する必要があります。
IT資産とは何か?
IT資産は、物理的な形態の有無によって、多岐にわたる対象を含みます。これらを網羅的に把握することが管理の第一歩です。
ハードウェア資産 企業のITインフラを構成する物理的な機器全般です。PC(デスクトップ、ノート)、サーバー、スマートフォン、タブレットといったエンドユーザー機器に加え、ネットワーク機器(ルーター、ファイアウォール、スイッチ)、プリンター、複合機、記憶媒体(USBメモリ、外付けHDD)など、企業が所有またはリースするすべての物理的資産が含まれます。
ソフトウェア資産 ハードウェア上で動作するプログラムやアプリケーションです。OS(Windows, macOS)、オフィススイート(Microsoft 365など)、会計ソフト、CRM/SFAツール、セキュリティソフトなどが該当します。ここで最も重要な管理対象が「ライセンス」です。購入形態(永続、サブスクリプション)、利用形態(デバイス単位、ユーザー単位、同時接続数単位など)が複雑化しており、これらの契約条件を正確に把握・遵守することが、コンプライアンスの観点から極めて重要になります。
その他のIT資産 物理的な形を持たない、無形の資産も含まれます。SaaSなどのクラウドサービス利用契約、独自ドメイン、サーバー証明書、IPアドレス、さらにはシステム構成情報や各種設定ファイル、運用マニュアルといった関連ドキュメントも、事業継続に不可欠な情報資産として管理対象に含めるべきです。
IT資産のライフサイクル管理
IT資産管理の核心は、これらの資産を「点」ではなく「線」で捉える、すなわち「ライフサイクル」全体を管理することにあります。
計画・調達:需要予測に基づき、どの資産を、いくつ、どのようなスペックで購入・契約するかを計画・決定する段階。
導入・展開:調達した資産をキッティング(初期設定)し、使用者や部署に割り当て、管理台帳へ正確に登録する段階。
運用・保守:資産の利用状況を監視し、OSやソフトウェアのアップデート、パッチ適用、故障時の修理・交換などを行う段階。
更新・再配置:リース期間満了や陳腐化に伴う機器の入れ替えや、異動・退職に伴う資産の回収と再割り当てを行う段階。
廃棄:物理的な廃棄やリース返却、ライセンスの解約を行う段階。データ消去を確実に行い、廃棄証明書などを保管することも重要です。
この一連の流れの中で、「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」利用しているかを常に最新の状態で追跡し続けることが、IT資産管理の目的です。
ITIL®におけるIT資産管理の位置づけ
こうした管理活動は、ITサービスマネジメント(ITSM)の国際的なベストプラクティス集である
「ITIL®(Information Technology Infrastructure Library)」においても、極めて重要な活動として位置づけられています。現在の最新バージョンである「ITIL 4」では、IT資産管理は独立した「IT資産管理プラクティス」として定義されています。旧バージョン(ITIL v3)では「サービス資産および構成管理(SACM)」という一つのプロセスに含まれていましたが、ITIL 4では資産の財務的価値やリスク、活用状況を管理し、その価値を最大化する活動として、よりビジネス貢献への焦点が当てられるようになりました。このように、IT資産管理は単なるモノの管理に留まらず、ビジネスに貢献するITサービスを提供するための基盤である、というグローバルスタンダードな視点を持つことが重要です。
IT資産管理がもたらす揺るぎないメリット
適切なIT資産管理体制を構築することで、企業は具体的かつ多大なメリットを享受できます。

メリット1:セキュリティとコンプライアンスの盤石化
管理が行き届いていないIT環境は、サイバー攻撃者にとって格好の標的です。例えば、OSのサポート期間が終了したPCを使い続けていると、脆弱性を突かれてマルウェア感染の起点となる可能性があります。IT資産管理ツールを使えば、ネットワーク上の全デバイスのOSバージョンやセキュリティパッチの適用状況を瞬時に把握し、危険な状態のPCを特定・隔離するといったプロアクティブな対策が可能です。
また、許可されていないソフトウェアのインストールを検知・ブロックする機能は、シャドーIT対策として非常に有効です。 コンプライアンス面では、特にソフトウェアライセンス管理が重要です。ライセンス監査はある日突然通知され、迅速な報告が求められます。その際に正確な台帳がなければ、保有ライセンス数とインストール数の突合ができず、不足が発覚すれば高額なペナルティだけでなく、企業の社会的信用の失墜にも繋がります。
確固たるIT資産管理は、こうした経営リスクに対する最も効果的な「保険」となるのです。
メリット2:ITコストの大幅な最適化
多くの企業では、IT資産の「見えない無駄」が経営を圧迫しています。
例えば、退職者が利用していたPCが倉庫に眠っていたり、部署の統廃合で使われなくなったソフトウェアライセンスが契約されたままになっていたりするケースは少なくありません。 IT資産管理を徹底すれば、こうした遊休資産や余剰ライセンスを可視化できます。新規にPCを購入する前に、まず遊休資産を再活用する。利用実態のないSaaSアカウントを解約する。これらを徹底するだけで、年間数百万円単位のコスト削減に繋がることも珍しくありません。
さらに、ハードウェアの機種ごとの故障率や、ソフトウェアの利用頻度といったデータを蓄積・分析することで、「安価だが故障が多いPC」や「高機能だがほとんど使われていないソフトウェア」などを特定し、将来の調達計画をデータに基づいて最適化することが可能になります。
メリット3:全社的な業務効率の劇的な向上
IT資産管理は、情シス担当者自身の業務を効率化するだけでなく、全社的な生産性向上にも貢献します。
例えば、従業員からPCのトラブルに関する問い合わせがあった際、管理台帳を参照すれば、そのPCのスペック、導入日、過去の修理履歴、インストールされているソフトウェアといった情報が即座に分かり、原因究明と解決までの時間を大幅に短縮できます。
また、従業員の入社・異動・退職に伴うPCやアカウントの準備・回収作業も、事前にプロセスが標準化され、台帳と連携することで、迅速かつミスなく行えるようになります。これにより、新入社員は入社初日からスムーズに業務を開始でき、情シス担当者は定型業務から解放され、DX推進といったより戦略的なミッションに時間を注力できるようになるのです。
IT資産管理、成功へのロードマップ(5つのステップ)
理論は分かっていても、何から手をつければよいか分からない、という方も多いでしょう。ここでは、IT資産管理を成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1:現状把握と管理対象の定義
最初に行うべきは、自社にどのようなIT資産がどれだけ存在するのかを徹底的に洗い出す「現状把握」です。この作業は情シスだけで行うのではなく、経理部門の固定資産台帳やリース契約書、各部署の利用者へのヒアリングなどを通じて、全社横断で情報を収集します。
その上で、管理の目的と費用対効果を考慮し、「何を、どこまで管理するのか」という管理範囲を明確に定義します。PCやサーバー、主要なソフトウェアは必須ですが、USBメモリやマウスといった少額の備品まで管理するかは、企業のセキュリティポリシーや管理工数と照らし合わせて判断します。 範囲が定まったら、収集した情報を「管理台帳」にまとめます。これが全ての基本となります。最低限、以下の項目は必須です。
ハードウェア管理項目例:管理番号、資産の種類、メーカー、モデル名、シリアル番号、CPU/メモリ/ストレージ等のスペック、購入日、購入元、価格、使用者、所属部署、設置場所、リース契約期間、保守契約情報、廃棄日など
ソフトウェア管理項目例:ソフトウェア名、バージョン、ライセンス形態(永続/サブスクリプション等)、保有ライセンス数、ライセンス証書保管場所、インストール先機器管理番号、購入日、価格など
ステップ2:管理体制と運用ルールの構築
IT資産管理は、ツールを導入すれば終わりではありません。継続的に情報を維持・更新するための「体制」と「ルール」が不可欠です。まず、IT資産管理の最高責任者を定め、情シス、総務、経理、各事業部門の役割と責任を明確にします。 その上で、資産のライフサイクル全体を網羅する運用ルールを文書化し、全社で共有します。
購入・導入時のルール:購入申請フロー、検収プロセス、台帳への登録手順
利用中のルール:ソフトウェアのインストール申請・承認フロー、情報変更時(異動など)の届出義務
返却・廃棄時のルール:退職時の返却手順、データ消去の基準、廃棄証明書の取得・保管
これらのルールを策定する際は、前述のITILなどのフレームワークが非常に参考になります。世界中の知見が詰まったベストプラクティスを参考にすることで、自社に合った実効性の高いルールを効率的に構築できます。
ステップ3:IT資産管理ツールの選定と導入
資産が100台を超えてくると、Excelでの手作業管理は限界を迎えます。情報の陳腐化、入力ミス、複数人での同時編集の困難さなど、多くの問題が発生し、管理しているつもりが実態と乖離していく「台帳の死」を招きます。 そこで不可欠となるのが「IT資産管理ツール」です。ツールは、ネットワーク上のPCやサーバーからハードウェア・ソフトウェア情報を自動収集し、台帳を常に最新の状態に保ってくれます。選定にあたっては、以下のポイントを比較検討しましょう。
機能要件:自社の管理対象(Windows, Mac, スマートフォン等)に対応しているか。ライセンス管理、セキュリティ機能(操作ログ取得、デバイス制御等)は必要か。
運用性:直感的なインターフェースか。クラウド型か、オンプレミス型か。
拡張性・連携性:他の社内システム(人事情報システム、会計システム等)と連携できるか。
サポート体制:導入支援や運用開始後のサポートは充実しているか。
複数の製品の資料請求やデモを試し、自社の課題と予算に最も合ったツールを選定することが重要です。
ステップ4:ライフサイクル管理の徹底した実践
ツールとルールが揃ったら、日々の運用を開始します。重要なのは、策定したルールを形骸化させず、ライフサイクルのあらゆる場面で徹底することです。例えば、新しいPCを調達したら、必ずキッティングの段階で管理ラベルを貼り付け、台帳に登録し、利用者情報と紐づけてから払い出す。従業員が異動したら、速やかに台帳の所属部署情報を更新する。退職者が出たら、PCやスマートフォンを確実に回収し、データ消去を行った上で台帳のステータスを変更する。こうした地道な運用の積み重ねが、台帳の鮮度と信頼性を維持します。
ステップ5:定期的な棚卸しとプロセスの見直し
どれだけツールで自動化し、ルールを徹底しても、台帳情報と物理的な現物との間には差異が生じることがあります。ネットワークに接続されていない機器、紛失、無断での持ち出しなど、自動収集だけでは把握できない例外を検出するため、年に1〜2回の物理棚卸しは依然として重要です。 棚卸しで判明した差異は、必ず原因を究明し、台帳を修正するとともに、なぜ差異が発生したのかを分析します。「ルールが複雑すぎて守られていなかった」「申請フローが形骸化していた」など、根本的な原因を突き止め、運用ルールやプロセスそのものを見直し、継続的に改善していくPDCAサイクルを回すことが、IT資産管理を成功させる最後の鍵となります。
まとめ:IT資産管理は「守り」から「攻め」の経営基盤へ
IT資産管理は、一度に完璧を目指す必要はありません。まずは自社の現状を正確に把握し、最もリスクや無駄が大きい領域(例えば、PCと主要ソフトウェアライセンス)からスモールスタートすることが成功への近道です。Excelでの台帳作成から始め、管理の重要性が社内で認識され始めた段階でツールの導入を検討するなど、成熟度に応じた段階的なアプローチが現実的です。
もはや、IT資産管理は単なるコストセンターや管理部門の業務ではありません。正確なIT資産の把握は、堅牢なセキュリティ体制の構築、コンプライアンス遵守、そして無駄のないIT投資を実現し、企業の経営資源を最大化します。それは、DX推進や新たなビジネス価値創造といった「攻めのIT戦略」を支える、揺るぎない土台となるのです。この記事が、皆さんの会社でIT資産管理を「守り」の業務から「攻め」の経営基盤へと昇華させる一助となれば幸いです。




